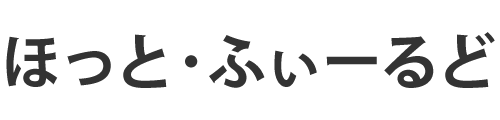-
Blog
-
Blogブログ
Blogブログ
2023.06.05ブログ
犬の毛玉のほぐし方とは?毛玉のできやすい犬種は?対策を紹介!

ワンちゃんに起きやすいトラブルとして毛玉が挙げられます。毛玉は放置してしまいがちですが、そのままにしておくと痛みが生じたり皮膚病になる可能性があります。「毛玉の原因ってなに?」「毛玉を予防するにはどうしたらいいの?」といった疑問を解消して、正しいお手入れ方法を知っておきましょう。
目次
- ○ 犬の毛玉の原因
- ○ 犬の毛玉を放置するとどうなる?
- ○ 毛玉ができやすい犬種とは?
- ・毛玉ができやすい場所
- ・毛玉ができやすい犬種
- ・クセも関係している?
- ○ 犬の毛玉のほぐし方、取り方
- ・ブラッシングと一緒にほぐそう
- ・毛玉の先からとかす!
- ・毛玉を梳かしましょう
- ・毛玉取り用ローションなども使用しましょう
- ・無理そうなときはトリミングサロンで切ってもらいましょう
- ○ 犬の毛玉の対策
- ・ブラッシングをしましょう
- ・定期的なシャンプー・トリミング
- ・濡れたら根元からしっかり乾かしましょう
- ○ まとめ
- ○ 横須賀のドッグトリミングサロンなら
ほっと・ふぃーるど!
犬の毛玉の原因

そもそも毛玉が何かわからない人も少なくないと思います。毛玉とは、汚れやブラッシング不足、シャンプー後の乾かしが足りずに水分を含んだ状態で被毛が絡み合うことでできる毛の玉のことをいいます。シャンプー後だけでなく、雨・雪の日のお散歩や夏場の水浴びのあともしっかり乾かす必要があります。
飼い主さんの中にも、朝起きたときや髪を長い間梳かしていないとき、特にロングヘアの方は櫛が通りにくいという経験があるのではないでしょうか?ワンちゃんの毛玉も同じことが起こっています。
犬の毛が抜ける原因とは?生え変わり?対策やお手入れを紹介します
犬の毛玉を放置するとどうなる?

毛玉を放置してしまうとその部分に汚れがたまっていきます。汚れは細菌の好物なので、細菌が繁殖し、不衛生な状態になってしまいます。そのまま炎症や皮膚病などになる可能性があります。また、毛玉で皮膚が引っ張られることで痛みが生じることがあります。そのまま毛が伸びていくことで皮膚が剥がれたりさけたりする場合もあるため、放置することは禁物です。
これから夏に向けて注意すべきことは蒸れることです。毛玉ができることで通気性が悪くなり、皮膚の蒸れにつながります。皮膚が蒸れることで皮膚病になる可能性があります。
犬のアレルギー性皮膚炎とは?原因や症状、治療方法について紹介します
毛玉ができやすい犬種とは?

毛玉のできやすさには毛質や毛量、クセなど個体差が関係していますが、一般的に毛玉のできやすい場所、犬種があります。当てはまらないからといって毛玉ができないわけではないので、愛犬に毛玉ができていないかチェックしてみましょう。
毛玉ができやすい場所
特に毛玉ができやすい場所として、犬が動いたときによく擦れる箇所が挙げられます。耳の根元や裏側、脇、足の内側などが挙げられます。また、お腹やお尻周りも毛玉ができやすい場所だといえます。お散歩の際に葉っぱがついていたりお座りする際に地面に触れる部位も毛玉ができやすいです。脇や足の内側はデリケートな部分なため、触られるのを嫌がるコもいます。
また、リードやお洋服で毛がこすれる場所も毛玉になりやすい場所です。毛が短い犬種でももつれができてしまいます。
毛玉ができやすい犬種
毛玉ができやすい犬種として、長毛で毛質が柔らかい犬種ほど毛玉ができやすいといわれています。よくいわれる犬種でいうとポメラニアンやシーズー、マルチーズやヨークシャーテリアなどです。また、プードルやシュナウザーはあまり毛は抜けないですが、お手入れしないと毛玉ができやすいので注意する必要があります。
トイ・プードルの特徴とは?カットの頻度や性格、飼う際のポイントについて紹介します!
クセも関係している?
実は愛犬のクセが毛玉のできやすさにつながっている場合もあります。特に身体を舐めるクセがあるコは注意が必要です。毛玉は水分を含んだ被毛が絡まり、そのまま乾燥することでできたり、絡まっている毛に水分が含まれることにより、一層毛玉が固くなります。そのため、舐めることで毛が湿った状態にあることが多いコは毛玉ができやすいといえます。
犬の毛玉のほぐし方、取り方
毛玉のほぐし方を順を追って紹介します。
ブラッシングと一緒にほぐそう
まずは毛玉以外の場所をブラッシングしてあげましょう。少しずつ毛玉近くを梳かすようにします。
毛玉の先からとかす!
周りのブラッシングが終わり、毛玉をほぐすときは毛玉の先からほぐします。
地肌が引っ張られないように、反対の手で押さえつつゆっくり優しく梳かします。
無理に梳かす、早く梳かすことは絶対NGです。
毛玉用の目の細かいコームを使うこともおすすめです。
毛玉を梳かしましょう
1.手を犬の身体に沿わせて人差し指と中指で挟むように毛玉を持ち、指を閉じます。コームを犬に対して直角にいれ、切るように梳かします。
2.ある程度ほぐれたら、毛玉の先から梳かすことを意識しながら、とかし進めます。
毛玉取り用ローションなども使用しましょう
頑固そうな毛玉には毛玉取り用ローションを使ってみましょう。スプレータイプのものもあり、多くのペットショップやオンラインショップで取り扱っています。
無理そうなときはトリミングサロンで切ってもらいましょう
梳かしてみて無理な時はトリミングサロンで切ってもらいましょう。特に根元から毛玉になっているときは切るのも犬が動いてケガしてしまう可能性があります。毛先近くで毛玉になっているときは、毛玉を三分割するように細かく切ります。根元から切ってしまうとその部分だけ短くなりますので注意が必要です。
犬の毛玉の対策

毛玉を予防するためにおうちではブラッシングをしましょう。ブラッシングに使用する道具はペットショップやオンラインショップで購入できます。
また、定期的にトリミングするとよいでしょう。シャンプー後はしっかり根元から乾かします。プードルやビションフリーゼなど、毛が伸び続ける犬種は定期的にカットしてあげることで愛犬も快適に過ごせます。
ブラッシングのやり方や道具についてまとめている記事がありますので、ブラッシングに挑戦してみましょう。
ブラッシングをしましょう
ブラッシングはお家でできる毛玉対策です。1~2,3日に1度ブラッシングをしてあげるだけで、毛玉を防ぐことができます。
ブラッシングの手順は以下の記事で詳しく解説しています。ブラッシングの道具はペットショップやオンラインサイトで購入することができます。
犬のブラッシングのやり方とは?効果や道具、子犬のブラッシングについて紹介します!
定期的なシャンプー・トリミング
定期的なシャンプー・トリミングも毛玉対策に有効です。毛玉が大きくなる前にお手入れすることで、健康に悪影響を及ぼすことを予防できます。
トリミングは犬種にもよりますが、1~1カ月半に1度を目安にしましょう。
プードルやビションフリーゼ、ヨークシャーテリアは毛が伸び続ける犬種なので、定期的にカットしてあげることで愛犬も快適に過ごすことができます。
犬のトリミングの頻度と役割、効果とは?メリット・デメリットを紹介します
濡れたら根元からしっかり乾かしましょう
お散歩中の急な雨、雪の日のお散歩、水浴びなど濡れるシーンがたくさんあります。濡れたときは自然乾燥ではなく、タオル、ドライヤーを使いしっかり根元から乾かしましょう。毛玉の原因になるだけでなく、皮膚状態の悪化につながります。
ブローの手順とポイントについて、下記の記事で詳しく解説しています。
まとめ

毛玉は汚れや擦れ、シャンプーやお散歩後の乾かし不足からできます。毛玉ができることにより、痛みが生じたり、蒸れたり汚れから細菌が繁殖することで皮膚病につながる可能性があります。長毛で毛が柔らかい犬種は毛玉ができやすいといわれてますが、プードルや柴犬といった毛の抜けない犬種だったり短毛種であっても毛のもつれや毛玉ができるため、お手入れする必要があります。毛玉を予防するためには日々のブラッシングと定期的なトリミングが大事です。愛犬が快適に過ごせるように正しくお手入れしましょう。
愛犬とアイコンタクトをしてみよう-アイコンタクトの様々なメリットと練習方法を解説-
横須賀のドッグトリミングサロンなら
ほっと・ふぃーるど!
「イメージ通りのカットにならなかった…」「愛犬がトリミングサロンに行くのを嫌がる…」そんなお悩みをお持ちの飼い主さんも少なくないのではないでしょうか?
神奈川県横須賀市の真ん中、衣笠にお店を構える当店は、パピーからシニア犬、小型犬から大型犬まですべての犬種に対応しております。
丁寧なヒアリングをこころがけ、完全予約制だからこそのこだわりのカット、施術を提供しております。
ぜひ以下のリンクからメニューや施術までの流れをご覧ください♪
投稿者プロフィール

最新の投稿
 ブログ2025年7月2日犬のおしり歩きの原因とは?下痢している時やトリミングの後するときは?
ブログ2025年7月2日犬のおしり歩きの原因とは?下痢している時やトリミングの後するときは? ブログ2025年6月18日犬のストレスサインは?原因や発散方法を紹介します
ブログ2025年6月18日犬のストレスサインは?原因や発散方法を紹介します ブログ2025年6月4日犬の誤嚥性肺炎とは?原因、予防について紹介します!
ブログ2025年6月4日犬の誤嚥性肺炎とは?原因、予防について紹介します! ブログ2025年5月21日トイ・プードルの特徴とは?カットの頻度や性格、飼う際のポイントについて紹介します!
ブログ2025年5月21日トイ・プードルの特徴とは?カットの頻度や性格、飼う際のポイントについて紹介します!
シェアする