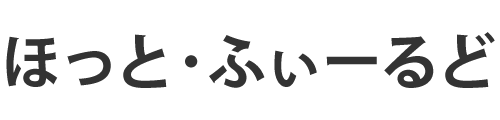-
Blog
-
Blogブログ
Blogブログ
2024.08.21ブログ
犬が水を飲まない7つの理由と危険な症状|脱水チェックと家庭でできる対策

犬が水を飲まないと「体調が悪いのでは?」「病院に連れて行くべき?」と不安になりますよね。水分不足は軽度なら心配不要な場合もありますが、脱水や病気のサインであることも。特に夏場やシニア犬では注意が必要です。この記事では、犬が水を飲まない7つの理由と病院に行く目安、そして家庭でできる効果的な対策を徹底解説します。
目次
- ○ 犬が水を飲まないときに危険な症状・すぐ病院に行くべきサイン
- ・犬の脱水症状チェック方法|皮膚・口・目で見分けるサイン
- ・犬の脱水が命に関わる理由と病院で伝えるべきポイント
- ○ 犬が水を飲まない7つの理由|安心できる場合と注意が必要な場合
- ・犬が水を飲まない理由① 水分はフードから足りている場合
- ・犬が水を飲まない理由② 季節や気温の影響
- ・犬が水を飲まない理由③ 体調不良や病気の可能性
- ・犬が水を飲まない理由④ 水や容器の汚れ
- ・犬が水を飲まない理由⑤ ストレスによるもの
- ・犬が水を飲まない理由⑥ 水を飲む場所や容器が合わない
- ・犬が水を飲まない理由⑦ 加齢による影響
- ○ 犬が水を飲まないときに疑われる病気とは?
- ・口内の病気(歯周病・腫瘍など)
- ・内臓の病気(腎臓病・肝臓病など)
- ・外傷や痛みによる影響
- ○ 犬にとって必要な飲水量の目安とチェック方法
- ・1日に必要な飲水量は体重1㎏当たり50~60ml!
- ○ 犬に必要な1日の水分量の目安は?飲水量を測ろう
- ○ 犬が水を飲まないときに試したい4つの対策
- ・水飲み場や容器を見直す
- ・水の温度を調整する
- ・フードから水分を補う
- ・香りや味をつけてみる
- ○ 犬が飲んでも大丈夫な飲み物とは?安全に与えられるものを解説
- ・基本は新鮮な水だけ
- ・犬用ミルクやヤギミルク
- ・薄めた無塩スープや経口補水液
- ○ 犬に絶対与えてはいけない危険な飲み物一覧
- ・牛乳や人間用の乳飲料
- ・カフェインを含む飲み物
- ・アルコール類
- ○ まとめ
- ○ 横須賀のドッグトリミングサロンならほっと・ふぃーるど!
犬が水を飲まないときに危険な症状・すぐ病院に行くべきサイン
水を飲まないことに加えて、下記の症状がある場合は病院に受診しましょう。
犬の脱水症状チェック方法|皮膚・口・目で見分けるサイン
犬が水を飲まないとき、以下の症状が見られる場合は脱水症状の可能性があります。
・皮膚に弾力がなく、つまむと硬く感じる
・鼻や舌、口の中が乾いている
・目が乾き、目やにが増えている
特に皮膚の状態は自宅でも簡単にチェックできます。
皮膚の戻りテスト(つまみテスト)
①背中の皮膚を軽くつまむ
②指を離す
③皮膚が元に戻るまでの時間を確認する
正常ならすぐに戻りますが、2〜3秒以上かかる場合は脱水のサインです。放置すると危険なため、早めに動物病院を受診してください。
犬の脱水が命に関わる理由と病院で伝えるべきポイント
脱水症状を放置すると、血液が濃くなり心臓に大きな負担がかかります。さらに内臓に十分な栄養や酸素が届かなくなり、肝臓や腎臓の機能障害、多臓器不全へと進行する危険もあります。重度の場合はショック症状を起こし、命に関わることもあるため注意が必要です。
動物病院を受診する際は、**「いつから水を飲んでいないか」「どんな症状が出ているか」**を具体的に伝えましょう。電話相談の段階で症状を説明すれば、優先的に診てもらえることもあります。
犬が水を飲まない7つの理由|安心できる場合と注意が必要な場合

愛犬が水を飲まない理由には大きく分けて7つあります。
心配のいらない理由から、少し様子を見るべき理由まで様々です。
どれに当てはまっているかチェックしてみましょう。
犬が水を飲まない理由① 水分はフードから足りている場合
ウェットフードやスープ仕立ての食事を与えている場合、食事から十分な水分を摂取しているため、水皿から飲む量が少なくなることがあります。これは自然なことなので、無理に飲ませようと心配する必要はありません。ただし、急に飲水量が減ったり、ドライフード主体なのに飲まない場合は注意が必要です。日常的に便や尿の状態をチェックし、水分不足の兆候がないか観察しましょう。
犬が水を飲まない理由② 季節や気温の影響
犬の飲水量は季節によって大きく変わります。夏は panting(ハアハアする呼吸)や足裏からの発汗で体内の水分が失われるため、飲水量が増える傾向があります。反対に冬は発汗量が少なく、寒さで冷たい水を嫌がる犬もいるため、飲水量が減りやすくなります。秋から冬にかけて「飲まないな」と感じても、体調に異変がなければ自然な変化の可能性があります。ただし、極端に飲まない場合は脱水のリスクがあるため要注意です。
犬が水を飲まない理由③ 体調不良や病気の可能性
口内炎や歯周病など口の中のトラブル、腎臓病や肝臓病など内臓疾患があると、水を飲むのを嫌がることがあります。また、外傷や関節痛などで水を飲む姿勢そのものが辛いケースもあります。単なる一時的な拒否ではなく、数日続く、食欲も落ちている、元気がないといった症状が併発している場合は病気の可能性が高いため、早めに動物病院を受診することが大切です。
犬が水を飲まない理由④ 水や容器の汚れ
犬は嗅覚が非常に優れているため、水のにおいやわずかな汚れにも敏感に反応します。容器がぬるついている、水を長時間放置していると飲まなくなることがあります。特に夏場は水が劣化しやすいため、1日数回は交換し、器もきちんと洗うことが重要です。また、素材によってにおいが残ることもあるため、陶器やステンレス製の容器がおすすめです。水の清潔さを保つことが、飲水量を増やす第一歩になります。
犬が水を飲まない理由⑤ ストレスによるもの
環境の変化や運動不足、騒音、見知らぬ人の訪問など、犬は日常のちょっとした変化にもストレスを感じやすい動物です。強いストレスがかかると食欲や飲水量が低下することがあります。特に神経質な性格の犬やシニア犬は影響を受けやすい傾向があります。生活環境をできるだけ安定させ、安心できる空間をつくってあげることが大切です。原因が思い当たらない場合は、体調不良と区別するために獣医師へ相談しましょう。
犬が水を飲まない理由⑥ 水を飲む場所や容器が合わない
水の置き場所が飲みに行きづらい場所だったり、容器の高さや深さが犬に合っていないと、水を飲むのを避けることがあります。特にトイレの近くや騒がしい場所は嫌がることが多いです。また、子犬やシニア犬は低すぎる容器だと首や関節に負担がかかるため、少し高さを出してあげると飲みやすくなります。飲み水は家の数か所に置くと自然に摂取しやすくなり、飲水量アップにもつながります。
犬が水を飲まない理由⑦ 加齢による影響
シニア犬になると喉の渇きを感じにくくなり、飲水量が減ることがあります。さらに運動量や代謝が低下し、活動時間も短くなるため、必要な水分量そのものが少なくなるのも特徴です。しかし飲まなさすぎると脱水や腎臓病のリスクが高まるため、工夫が必要です。フードをふやかす、常温の水を与える、器を複数の場所に置くなど、日常生活で取り入れられる工夫を試すことで改善につながります。
犬が水を飲まないときに疑われる病気とは?

水を飲まないことで疑われる病気が大きく分けて3つあります。
口内の病気(歯周病・腫瘍など)
犬が水を飲まない原因として、口の中のトラブルが考えられます。歯周病や口内炎、口腔内の腫瘍があると、飲むときに痛みを感じるため水を避けてしまいます。また、口臭の悪化やよだれの増加などもサインです。軽度の歯周病は歯みがきやスケーリングで改善できますが、腫瘍の場合は早期発見が重要です。水を飲まないだけでなく、食欲が落ちている、口周りを気にしている場合は動物病院での検査をおすすめします。
内臓の病気(腎臓病・肝臓病など)
腎臓や肝臓の病気は水分代謝に関わるため、水を飲む行動に変化が出やすいです。初期では水をよく飲むケースもありますが、進行すると体調が悪化し水を飲まなくなることがあります。特に腎不全や尿路結石、膀胱炎などは脱水と深く関係しており、放置すると命に関わることも。元気がない、尿の量や色が変化した、食欲が落ちたといった症状がある場合はすぐに受診を。早期診断・治療が予後を大きく左右します。
外傷や痛みによる影響
犬が怪我や関節のトラブルを抱えていると、水を飲む姿勢を取るのが辛くなり、飲水量が減ることがあります。特に小型犬に多い椎間板ヘルニアは、首や背中に痛みが出て水皿に顔を近づけにくくなるため要注意です。また、足腰の痛みや脱臼なども同様に影響します。歩き方がおかしい、鳴き声が増えた、触ると嫌がる場所があるなどの変化が見られたら、すぐに獣医師に相談しましょう。飲まないことの裏に隠れた痛みを見逃さないことが大切です。
犬にとって必要な飲水量の目安とチェック方法

ここまで水を飲まない理由や水を飲まないときに疑われる病気について解説してきました。「どれくらい飲んでいれば大丈夫なの?」と思った飼い主さんも多いのではないでしょうか。ここでは、愛犬に必要な水の量を計算してみましょう。
夏に向けて紫外線対策はばっちりですか?注意すべきポイントとは!
1日に必要な飲水量は体重1㎏当たり50~60ml!
健康なワンちゃんの一日の飲水量は体重1kgあたり50~60mlだといわれています。
愛犬の体重が5㎏の場合、5×50~60で、250~300mlになります。
必ず飲ませないといけないということではなく、あくまで目安ですので、達していなくても脱水など起こしていなければ様子見をしましょう。ウェットフードなどからも水を吸収している場合も多く、飲水量が多少少なくても問題ないケースもあります。逆に、運動量が多いワンちゃんはさらに必要になります。大切なのは、ワンちゃんにあわせた水分量を取る、ということです。
犬に必要な1日の水分量の目安は?飲水量を測ろう
次に、愛犬の一日の飲水量を確認してみましょう。
①水の量を測ってから飲み水用の器に入れる
②24時間経過した時点で、残っている水の量を測る
③器に入れた量から残っている量を引き算する
器の中が空にならないようにつぎ足すことがポイントです。この時も何ミリリットル足したのか記録しておきましょう。また、天気や湿度によって飲水量が変わります。一週間ほど記録することで、愛犬の平均的な量がわかります。すべて飲んでいるわけではなく、少なからず蒸発している分が含まれています。
また、おしっこの量やうんちの硬さもチェックすることで、水分量が足りていないかチェックすることができます。
犬が水を飲まないときに試したい4つの対策

愛犬が極端に水を飲んでいなかったり、何日も少ないという場合は以下の対策をしてみましょう。
水飲み場や容器を見直す
水を飲まない原因のひとつに「環境」があります。水皿がトイレの近くだったり、普段行かない場所に置いてあると犬は飲みづらく感じます。また、プラスチック容器はにおい移りや傷による雑菌繁殖が起こりやすいため、陶器やステンレス製がおすすめです。複数の場所に置いたり、高さを調整するだけでも改善されるケースがあります。まずは環境を整えることから始めましょう。
水の温度を調整する
犬によって好む水温は異なります。夏場は氷を入れて冷たく、冬はぬるま湯にしてあげると飲みやすくなることがあります。特に寒い季節は冷たい水を嫌う犬が多いため、常温や人肌程度の温度にしてあげるのが効果的です。自動給水器を利用すると温度管理がしやすいタイプもあるため、選ぶ際のポイントにしてみましょう。温度を少し変えるだけで飲水量が改善することは珍しくありません。
フードから水分を補う
どうしても水を飲まない場合は、食事で補うのもひとつの方法です。ドライフードをぬるま湯でふやかす、ウェットフードに切り替える、スープ仕立ての手作り食を加えるなど、水分を自然に摂れる工夫を取り入れましょう。ただし味付けは不要で、人間用の調味料は厳禁です。フードからの水分補給は特にシニア犬や子犬に有効で、飲水拒否が続くときに安心して使える方法です。
香りや味をつけてみる
水そのものを嫌がる犬には、鶏肉や野菜を茹でたゆで汁などを薄めて加えると飲みやすくなることがあります。犬用ミルクやペット用の経口補水液も市販されていますので、必要に応じて利用しても良いでしょう。ただし塩分や糖分を含む人用スポーツドリンクは厳禁です。ほんの少し香りや味をプラスするだけで、興味を持って飲むようになる犬は多いため、一度試してみる価値があります。
犬が飲んでも大丈夫な飲み物とは?安全に与えられるものを解説

お水を飲みたがらない場合、お水以外の液体を飲ませてみましょう。
ここではワンちゃんが飲んでも大丈夫なモノ、だめなものについて解説します。
基本は新鮮な水だけ
犬にとって最も安全で必要不可欠なのは新鮮な水です。水は体温調整や代謝、臓器の働きを支えるために欠かせません。人間と違い、犬にとって水以外の飲み物は基本的に不要です。特に夏場は雑菌の繁殖が早いため、こまめに交換して清潔な状態を保つことが大切です。冷たすぎる水や長時間放置された水は下痢の原因になることもあるため、常温で新鮮な水をいつでも飲める環境を整えてあげましょう。
犬用ミルクやヤギミルク
水をあまり飲まない犬や食欲が落ちているときには、犬専用のミルクやヤギミルクを利用するのも有効です。カルシウムやタンパク質を補えるうえ、風味がよく犬の嗜好性も高いのが特徴です。ただし、牛乳や人間用の加工乳は乳糖不耐症による下痢や嘔吐のリスクがあるためNGです。必ず「犬用」と記載のある商品を選び、あくまで補助的に与える程度にとどめましょう。主食や水の代わりにはなりません。
薄めた無塩スープや経口補水液
食欲が落ちているときや脱水が心配なときには、薄めた無塩の鶏スープや、犬用の経口補水液が役立ちます。香りが立つため飲みやすく、水分と一緒に電解質も補えるのがメリットです。ただし人間用のスポーツドリンクや味付きのスープは塩分や糖分が多すぎて危険です。必ず「犬専用」のものを選びましょう。普段は水を中心に与え、体調不良や特別なシーンでのみ利用するのが理想的です。
犬に絶対与えてはいけない危険な飲み物一覧
牛乳や人間用の乳飲料
犬は乳糖を分解する酵素が少ないため、牛乳や人間用の乳飲料を飲むと下痢や嘔吐を引き起こすことがあります。特に子犬やシニア犬は消化機能が弱く、体調を崩すリスクが高いので注意が必要です。カルシウム補給のつもりで与えてしまう飼い主もいますが、代わりに犬用ミルクやヤギミルクを選べば安心です。「牛乳=健康に良い」という思い込みは危険なので避けましょう。
カフェインを含む飲み物
コーヒーや紅茶、緑茶などのカフェインを含む飲み物は犬にとって非常に危険です。少量でも神経や心臓に負担をかけ、中毒症状を引き起こすことがあります。主な症状は落ち着きがなくなる、震える、嘔吐、下痢、頻脈などで、重症化すると命に関わるケースもあります。飼い主が飲んでいるものを誤って舐めることも多いため、テーブルに放置しないよう徹底して管理しましょう。
アルコール類
アルコールは犬にとって猛毒であり、絶対に与えてはいけません。体内に入るとごく少量でも中枢神経を抑制し、意識障害や呼吸不全を引き起こす恐れがあります。アルコールを含む甘いお菓子や果実酒を舐めただけでも危険です。特に体の小さい犬は重症化しやすいため、家でお酒を楽しむ際には愛犬の手が届かない場所で管理しましょう。万が一口にした場合は、すぐに動物病院へ連絡することが重要です。
まとめ
犬が水を飲まない理由には「気候や食事内容など心配いらないもの」から「体調不良や病気が疑われるもの」までさまざまです。大切なのは、飲水量の目安(体重1kgあたり50〜60ml)を把握し、愛犬の状態に合わせてチェックすることです。水を飲まないときは、容器や温度を工夫する、フードで水分を補うなどの対策も効果的ですが、それでも改善しない場合や危険なサイン(脱水・ぐったり・食欲不振など)がある場合は、迷わず動物病院を受診してください。日頃から清潔な水を用意し、愛犬が安心して水分補給できる環境を整えることが、健康を守る一番の近道です。
横須賀のドッグトリミングサロンならほっと・ふぃーるど!
「イメージ通りのカットにならなかった…」「愛犬がトリミングサロンに行くのを嫌がる…」そんなお悩みをお持ちの飼い主さんも少なくないのではないでしょうか?
神奈川県横須賀市の真ん中、衣笠にお店を構える当店は、パピーからシニア犬、小型犬から大型犬まですべての犬種に対応しております。
丁寧なヒアリングをこころがけ、完全予約制だからこそのこだわりのカット、施術を提供しております。
ぜひ以下のリンクからメニューや施術までの流れをご覧ください♪
投稿者プロフィール

最新の投稿
 ブログ2026年1月7日犬はみかんを食べられる?与えていい量・注意点とみかんジュースはNGな理由
ブログ2026年1月7日犬はみかんを食べられる?与えていい量・注意点とみかんジュースはNGな理由 ブログ2025年12月17日犬のシャンプー後に乾かない原因3つ|正しいタオルドライとドライヤーの完全ガイド
ブログ2025年12月17日犬のシャンプー後に乾かない原因3つ|正しいタオルドライとドライヤーの完全ガイド お知らせ2025年12月7日【年末年始のお休みのお知らせ】
お知らせ2025年12月7日【年末年始のお休みのお知らせ】 ブログ2025年12月3日【完全版】トリミングに行けない犬の“伸びすぎ対処法”|自宅ケア完全ガイド
ブログ2025年12月3日【完全版】トリミングに行けない犬の“伸びすぎ対処法”|自宅ケア完全ガイド
シェアする